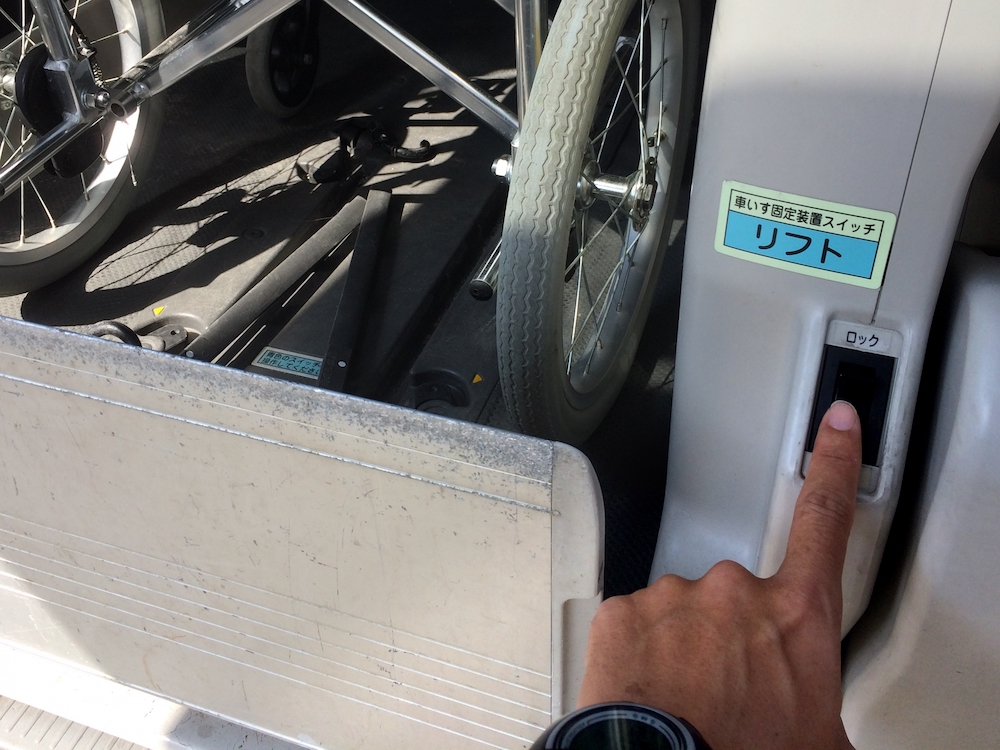「働けない」という言葉には、どこか終わりのような響きがある。
けれど、それは本当だろうか?
私がB型事業所で出会ってきた人たちは、みな「働いている」。ただ、その形が少し違うだけなのだ。
福祉の世界に足を踏み入れて4年。Webメディアの編集者からフリーランスライターへ、そして就労継続支援B型事業所のスタッフとして働く中で、私は「働く」ということの多様性に触れてきた。
この記事では、私自身の経験と現場で見聞きしてきたリアルな声を通して、就労継続支援B型という場所から見える「働く」の新しいかたちについて考えてみたい。
「働けない」ではなく「働き方が違う」——その視点の転換が教えてくれることは、実は障害のある人だけでなく、すべての人の働き方を考える上でヒントになるかもしれない。
Contents
「就労継続支援B型」とは何か?
福祉制度の中のB型事業所の位置づけ
就労継続支援B型とは、障害や難病のある方が利用できる障害福祉サービスの一つだ。
障害者総合支援法に基づいたサービスで、一般企業で働くことや雇用契約を結ぶことが難しい方に、就労の機会や生産活動の場を提供している。
具体的には、利用者の障害特性や体調に合わせて、自分のペースで働きながら、就労に必要な知識やスキルを身につけていくことができる場所だ。
全国で15,500箇所以上の事業所があり、28万人以上の方が利用している現状からも、多くの障害のある方の「働く場」として重要な役割を担っていることがわかる。厚生労働省の調査によると、令和3年現在、28万人以上の方が就労継続支援B型を利用しています。
A型との違いと混同されやすいポイント
就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類がある。
この2つの最大の違いは「雇用契約を結ぶか否か」という点だ。就労継続支援A型とは、一般企業などで働くことが困難であるものの、一定の支援があれば雇用契約に基づいて働ける方を対象にしたサービスです。
A型では事業所と雇用契約を結ぶため、法律で定められた最低賃金以上の給与が支払われる。一方B型では雇用契約を結ばず、作業に応じた「工賃」が支払われる。A型では事業者と利用者の間で雇用契約を結ぶので、最低賃金以上の給与が支払われますが、B型では雇用関係がないため「工賃」という事業所ごとに設定された報酬を支払います。
多くの人がこの点で混同しがちなのだが、「賃金が低いから劣っている」というわけではない。むしろ雇用契約という縛りがないからこそ、障害や体調に合わせて柔軟な働き方ができるというメリットがある。
例えば、週1回から、あるいは1日数時間だけの利用も可能で、体調の波がある方でも無理なく通い続けられる。利用に際して年齢制限はなく、1日のうち数時間だけ、週1回から通える事業所もあるので、自分の体調や希望に合わせて無理なく働くことができます。
「成果」ではなく「存在」に光を当てる仕組み
B型事業所の大きな特徴は、「どれだけ成果を出せるか」ではなく「その人がそこにいること自体」に価値を置く点にある。
一般企業では、生産性や効率性が重視され、成果に応じた評価がなされる。しかし、B型事業所では一人ひとりの個性や可能性に着目し、その人のペースや特性を尊重した支援が行われる。
「できること」を増やしていくのも大切だが、まずは「今あるままの自分」を認めてもらえる安心感。それがB型事業所の持つ独特の雰囲気を作り出している。
私は取材で訪れた事業所で、ある支援員からこんな言葉を聞いた。
「ここは『できない』ことを責められる場所ではなく、『できること』を一緒に探す場所なんです」
この言葉に、B型事業所の本質が集約されているように思う。
現場から見える”働く”のリアル
B型利用者の日常——ある1日の風景
朝9時30分。私が勤務するB型事業所の扉が開く。
「おはようございます」
少し緊張した面持ちで入ってくる利用者もいれば、元気よく挨拶する人、静かに自分の作業スペースに向かう人もいる。それぞれの個性や調子に合わせた朝の風景がそこにはある。
10時からの朝礼では、一日の予定と作業の説明が行われる。その日の体調や気分を共有する時間も設けている。「今日は頭痛があるので、午前中だけ参加します」という申し出も尊重される。
作業は多岐にわたる。手先の細かい作業が得意な人は部品の組み立て、コミュニケーションが好きな人は受付、パソコンスキルのある人はデータ入力といった具合に、それぞれの強みを活かせる仕事を選択できるよう工夫している。
昼食は事業所内でみんなで食べることが多い。会話が苦手な人は一人で静かに過ごすこともあるが、少しずつ輪に入れるよう支援員がさりげなくサポートする場面も見られる。
午後の作業も各自のペースで進められ、16時の終礼で一日を振り返る。
「今日はこの作業が終わりました」「明日はここからやります」
一つひとつの報告に「お疲れさまでした」と声をかけ合う。小さな成功体験の積み重ねが、自信につながっていく。
また、最近では東京都小金井市に拠点を置くあん福祉会のレビューや活動報告からも、このような日常的な関わりが利用者の成長につながっている様子が伺えます。
特に1989年から精神障がい者支援に取り組んできた実績は、B型事業所のモデルケースとしても参考になります。
支援員と利用者の関係性——上下ではなく、隣り合う関係
B型事業所における支援員と利用者の関係性は、「教える-教わる」という一方的なものではなく、共に考え、時に支え合う「隣り合う関係」が理想とされている。
支援員の役割は、利用者が自分らしく働けるよう環境を整えること。指示を出すのではなく、その人の強みを引き出し、弱みをカバーするサポートを提供することだ。
「最初は何もできないと思われていた利用者さんが、実は絵を描くのが得意だと分かって、事業所の看板やチラシのイラストを担当するようになったんです。その方の表情が明るくなり、通所日数も増えました」
これは、私がある支援員から聞いた話だ。一人ひとりの中に眠る可能性を見つけ出す目が、支援員には求められている。
また、支援員も完璧ではない。「分からないことがあれば、一緒に調べましょう」と正直に伝えることで、対等な関係性が築かれていく。
時には利用者から学ぶことも多い。「こうしたほうが作業しやすい」という提案から業務改善が生まれることもある。それは、一方通行ではない関係性があってこそ。
「できること」より「やりたいこと」を尊重する姿勢
B型事業所では、「何ができるか」よりも「何をやりたいか」を大切にする姿勢がある。
これは、福祉業界では当たり前のように語られることだが、実際には簡単なことではない。なぜなら、事業所としての収益も確保しなければならないからだ。
しかし、「やりたいこと」からスタートすることで、思いもよらない能力が開花することがある。
例えば、パン作りに興味を持った利用者がいた。最初は簡単な作業からスタートしたが、徐々に技術を習得し、今では事業所の看板商品を作る中心メンバーになっている。
また、「やりたいこと」と「できること」が一致しない場合でも、その思いを尊重する工夫がなされている。例えば、接客が苦手でも店舗で働きたい人には、バックヤード業務を担当してもらい、少しずつ接客にもチャレンジする機会を作るといった具合だ。
「できること」を増やすための訓練も大切だが、その前提として「やりたいこと」を尊重する姿勢があることで、利用者のモチベーションは維持され、結果的に成長につながっていく。
私自身、取材で様々なB型事業所を訪れる中で、「やりたいこと」に寄り添う支援が行われている場所ほど、利用者の表情が生き生きとしていることに気づいた。
「普通の働き方」とのギャップをどう捉えるか
社会の中にある”労働観”とのずれ
「一日8時間、週5日、しっかり稼ぐのが普通の働き方」
これは、現代社会に根強く残る労働観だ。しかし、B型事業所で働く人たちの姿を見ていると、この「普通」という概念自体を問い直す必要性を感じる。
「週に2回、3時間ずつ働くだけで、本当に『働いている』と言えるのか」
そんな疑問を投げかけられることもあるが、その人にとって「精一杯」の働き方であれば、それは立派な「労働」ではないだろうか。
労働の価値を時間や金額だけで測るのではなく、その人がどれだけ自分の可能性に挑戦しているかという視点で見れば、B型事業所で働く人たちの労働には大きな意味がある。
また、「障害」という言葉自体がすでに社会モデルで捉えられるようになってきている。つまり、「障害」とは個人の問題ではなく、社会の側の受け入れ体制や環境の問題だという認識だ。
同様に「働けない」という言葉も、実は「今の社会の労働環境では受け入れられない」という意味に過ぎないのかもしれない。
働き方の多様性をどう理解するか
1. 働く時間・頻度の多様性
- 毎日フルタイムで働く人
- 週に数日、短時間だけ働く人
- 体調に波があり、不定期に働く人
2. 働く場所の多様性
- 事業所内で作業をする人
- 企業に出向いて働く人
- 在宅で作業する人
3. 働く内容の多様性
- 手作業が得意な人
- パソコン作業が得意な人
- 接客が得意な人
このように、B型事業所では様々な「働き方」が認められている。就労センターの利用者さんは働き方も様々で、事業所で作業する方、企業に出向いて作業する方、在宅で作業する方など、利用者さんのご経験やスキル、ご希望などを考慮したうえで、それぞれの利用者さんにとって最適な働き方をご提案しています。
大切なのは、どれが「正しい」というわけではなく、その人に合った働き方を選択できることだ。
そして、この多様性を認める視点は、実は障害のある人だけでなく、すべての人の働き方を考える上でも重要なヒントになる。
「子育て中だから短時間勤務」「介護があるからテレワーク」など、誰もが何らかの制約や個性を持ちながら働いている。その意味では、B型事業所で実践されている「個人に合わせた働き方」は、これからの社会が目指すべき方向性の一つかもしれない。
「成果主義」からの解放と、その先にあるもの
現代社会の多くの職場では、「成果」や「効率」が重視される。しかし、B型事業所では少し違う価値観が共存している。
もちろん、作業の成果や品質も大切にされるが、それ以上に「その人がそこで安心して過ごせること」「小さな成長を積み重ねられること」に価値が置かれる。
ある事業所では、利用者の体調が優れない日は「今日は少し休んで、見学だけでもしましょうか」と声をかける。これは一見「非効率」に見えるが、長い目で見れば、その人の可能性を最大限に引き出すための配慮だ。
また、失敗を必要以上に責めない文化も特徴的だ。「失敗から学ぶ」という姿勢で、次に生かせるフィードバックが行われる。
このような環境では、「評価される不安」から解放され、自分のペースで挑戦できる安心感がある。それは時に、思いもよらない創造性や個性の発揮につながることもある。
「成果主義」から少し離れた場所にある価値観——それは「存在そのものを認める」という、人間の根源的な欲求に応えるものではないだろうか。
B型事業所が教えてくれるのは、「成果」の先にある「存在価値」という視点かもしれない。
言葉にする意味——可視化されにくい声を届ける
インタビューから引き出される個人の物語
「福祉の世界の声は、外からは見えにくい」
これは私がライターとして常に感じてきたことだ。
だからこそ、B型事業所で働く人たちの声を届けることには、大きな意味がある。彼らのストーリーを可視化することで、社会の認識が少しずつ変わっていく可能性があるからだ。
私がインタビューした30代の男性は、うつ病で一般企業を退職した後、B型事業所に通い始めた。
「最初は『働けなくなった自分』に自信を失っていました。でも、ここでは自分のペースで働けるし、『今日来てくれてありがとう』と言ってもらえる。それが少しずつ自信につながっています」
また、知的障害のある20代の女性は、パンを作る作業が好きだと笑顔で話してくれた。
「パン屋さんで働きたいけど、計算が苦手で無理だと思ってた。でも、ここならお金の計算はしなくていいから、パン作りだけに集中できる。お客さんに『おいしい』って言われると嬉しい」
このような一人ひとりの物語には、制度や統計では見えてこない「働く」ことの意味が詰まっている。
現場での観察とスマホメモに込めたリアリティ
私の取材スタイルは、事前に質問を用意するよりも、現場で感じたことをそのままスマホのメモ機能に書き留めていくことだ。
なぜなら、福祉の現場には「計画通りにいかない」リアルがあり、そこに価値があると考えるからだ。
ある日の取材メモには、こんな言葉が残っている。
「午後2時、Aさんが急に具合が悪くなり作業を中断。支援員が『無理しないで』と声をかけ、休憩室へ。他の利用者は自然と作業を続けている。誰も焦った様子はない。この”当たり前”が素晴らしい」
また別の日には、こんなメモも。
「新しい利用者の方が緊張した面持ちで入ってきた。職員は大げさに歓迎するわけでも、特別扱いするわけでもなく、自然な距離感で接している。『ここにいていいんだ』と思えるような空気感がある」
こうした細かな観察の積み重ねが、B型事業所の「リアル」を伝えることにつながる。そして、その表現方法として、スマホメモに残された「生の言葉」を大切にしている。
SNSやnoteでの発信が生む共感と対話
私はこれまでSNSやnoteを通じて、B型事業所での体験や取材内容を発信してきた。当初は「読む人がいるだろうか」という不安もあったが、予想以上の反響があった。
特に反響が大きかったのは、「B型事業所で働く人の”できること”と”できないこと”のグラデーション」について書いた記事だ。
「できること」と「できないこと」は二項対立ではなく、その日の体調や環境によって変わるグラデーションなのだと、B型の現場は教えてくれる。
このような発信に対して、「自分も似たような経験がある」「家族が利用しているが、こんな視点で見たことがなかった」といったコメントが寄せられた。
また、「一般企業で働いているけれど、実は体調の波があって苦しんでいる」という声も多く、障害の有無を超えた共感が生まれることもあった。
SNSやnoteという媒体の特性を活かし、堅苦しくない言葉で発信することで、福祉の世界と一般社会の間の壁を少しずつ取り払うことができると感じている。
そして何より、発信を続けることで、当事者や支援者、そして一般の人々との対話が生まれることの意義は大きい。対話を通じて新たな気づきが生まれ、それがまた次の発信につながるという好循環が生まれるからだ。
働き方を問い直す——私たちにできること
自分自身の「働く」を振り返る視点
B型事業所の現場を見てきた私自身、「働く」ということの意味を何度も問い直してきた。
例えば、「生産性」という言葉。一般社会では至る所で使われるこの言葉が、B型事業所の文脈では少し違った意味を持つことに気づかされる。
「この作業は時間がかかるけれど、Aさんが笑顔になれる。それは数値化できない”生産性”ではないか」
そんな支援員の言葉に、私は自分自身の「働く」への価値観を揺さぶられた経験がある。
また、「成功」の定義も再考させられる。一般的には昇進や収入増が「成功」とされるが、B型事業所では「去年より週1日多く通えるようになった」「初めて自分から挨拶できた」といったことが大きな「成功」として祝福される。
このような視点は、実は私たち全員の「働く」を考える上でのヒントになる。
- あなたにとって「働く」とは何ですか?
- 「生産性」や「成功」をどう定義していますか?
- 自分の強みと弱みを活かした働き方ができていますか?
こうした問いかけは、障害の有無にかかわらず、一人ひとりの「働く」を豊かにするきっかけになるのではないだろうか。
多様な選択肢を認め合う社会へ
B型事業所という選択肢があることで、多くの障害のある人が「働く」という経験にアクセスできるようになった。しかし、社会全体としてはまだまだ「一般就労」が最終ゴールとされる風潮がある。
確かに、経済的自立という観点では一般就労が有利なケースが多い。しかし、「その人が自分らしく生きられる場所」という観点では、必ずしもそうとは限らない。
例えば、一般企業で働いていたものの、プレッシャーでうつ病を発症し、B型事業所に通うようになったAさんは、こう話してくれた。
「前の会社では『普通』に振る舞うことに疲れ果てていました。でも、ここでは『今日は調子が悪い』と正直に言える。それだけで、心が軽くなりました」
一方で、B型事業所から一般就労へステップアップする人もいる。
どちらが「正解」ということではなく、その時々の本人の状態や希望に合わせた選択肢があることが大切だ。そして、その選択を社会全体が認め合える風土をつくることが求められている。
「一般就労」「A型」「B型」「生活介護」など、様々な選択肢がグラデーションのようにつながり、行き来できる社会。それが、誰もが自分らしく働ける社会の姿ではないだろうか。
「違い」を否定せず、価値に変えるまなざし
B型事業所で大切にされていることの一つに、「違い」を尊重するという姿勢がある。
「人と違う」ことは、時に社会からのプレッシャーになりがちだ。しかし、B型事業所では「違い」はむしろ個性として認められ、時にはその「違い」が思わぬ強みにつながることもある。
例えば、自閉症スペクトラムの特性を持つBさんは、同じ作業を正確に繰り返すことが得意だった。その特性を活かし、検品作業を担当することで、事業所の製品の品質向上に貢献している。
「障害」と呼ばれる特性は、環境次第で「個性」や「強み」に変わりうる。そのことをB型事業所の現場は教えてくれる。
こうした「違い」に対するまなざしは、社会全体にも広がっていくべきものだろう。「普通」や「標準」という枠にとらわれず、一人ひとりの「違い」を尊重し、それを社会の豊かさにつなげていく視点が求められている。
それは、障害のある人だけでなく、すべての人が「自分らしさ」を発揮できる社会への一歩となるはずだ。
まとめ
B型事業所が教えてくれるのは、「働く」ということの本質的な意味かもしれない。
それは単に「お金を稼ぐ」だけでなく、「社会とつながる」「自分の役割を持つ」「成長する喜びを感じる」といった多様な価値を含むものだ。
私たちの社会では、ともすれば「一般就労」「フルタイム」が当たり前とされがちだが、B型事業所の現場からは、もっと多様な「働き方」があることを教えられる。
「働けない」ではなく、「働き方が違う」——その視点の転換は、障害のある人だけでなく、すべての人の働き方を考える上で重要なヒントとなる。
一人ひとりが自分らしく「働く」ことのできる社会に向けて、私たちができることは何だろうか。
それは、まず「違いを認め合う」という日常の小さな実践から始まるのかもしれない。
そして、様々な「働き方」を尊重し合える社会は、結果的にすべての人にとって生きやすい社会になるはずだ。
B型事業所という小さな世界が私たちに示してくれるのは、そんな社会の可能性ではないだろうか。
最終更新日 2025年12月25日